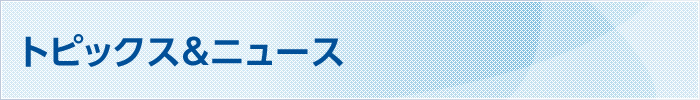
東京・世田谷区のサザエさん一家の銅像に対する課税問題で、都は年60万円の固定資産税を
銅像に課す方針から一転、課税免除を決めました。
納付済みの15万円を除く45万円が免除されたそうです。
サザエさん一家の銅像への課税問題は、銅像12体を所有していた桜新町商店街振興組合に対して、
都が今年6月3日付けで「固定資産税納税通知書(償却資産税)」を届けたことが発端。
この通知書には計算内訳明細の記載がないため、商店街振興組合が問い合わせたところ、
銅像12体に対する税額が含まれていることが分かりました。
世田谷都税事務所の判断は、銅像が商店街のPRのための事業用資産というものです。
銅像の取得価額が合計約4千万円で、このうち都と区が補助金約2800万円を支出していました。
銅像部分の償却資産額を計算すると、耐用年数45年の建築物として、累計約983万円を納税することになっていました。
商店街振興組合は、銅像の目的は商店街のPRではなく地域振興であると説明。
また、銅像の無償貸与契約を区と締結しました。これらが認められ、課税免除になりました。
ちなみに、鳥取・境港市の水木しげるロードに設置された妖怪153体や、
東京・葛飾区の亀有商店街に立つ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の登場人物14体の銅像には、
償却資産税は課税されていませんでした。
その①からの続きです
そこで、有望事業・産業の成長加速やグローバル市場での勝ち残りを目指す企業について、
課税負担の軽減措置を講じる制度の創設を求めております。
「企業のベンチャー投資促進税制」は、事業拡張期のベンチャー企業への資金供給拡大のため、
経営・技術指導を行うベンチャーファンドへ出資する企業について、投資リスクに備えるための税制上の支援措置を講じます。
ベンチャー企業が大きく成長するためには、事業拡張期において、製品等の量産体制確立や販路拡大等が必要なため、
大規模な資金供給能力や経営ノウハウを持つベンチャーファンド・事業会社の支援が有効との考えです。
そのほか、民間研究開発投資を今後3年以内に対GDP比で世界一に復活すべく、
研究開発税制の増加型上乗せ措置の控除率を現行の5%から30%に引き上げるなど
拡充・延長や中小企業の生産性向上を促すため、中小企業投資促進税制におけるソフトウェアや
関連設備等に係る特別償却率を現行の30%から即時償却に、税額控除を現行7%から12%への引上げ等の拡充を要望しております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年10月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、
記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
経済産業省は、2014年度税制改正に関する要望を公表しました。
それによりますと、
①生産性向上を促す設備等投資促進税制の創設
②事業再編を促進する税制の創設
③企業のベンチャー投資促進税制の創設といった成長戦略関連の項目が中心となっています。
経済産業省は、今後3年間で国内設備投資額年間約70兆円への回復を目指しており、
「生産性向上を促す設備等投資促進税制」は、先端設備の導入、生産ラインやオペレーションの刷新・改善など
「質」の高い投資について、即時償却・税額控除等の税制措置を講じます。
対象設備は、先端的な「機械・装置」に加え、生産性向上に資する「ソフトウェア」、
「器具・備品」・生産ラインやオペレーションと一体となった「建物」などです。
「事業再編を促進する税制」は、わが国では1つの事業部門に多くの事業者が存在し、
その利益率は極端に低くなっている状況にあることから、自社の事業部門を切り出し、
他社の事業部門と統合することにより、規模の拡大や技術の補完による新市場展開・競争力強化につながるとの考えです。
◆収用等による資産の譲渡課税
収用等により資産を譲渡し、補償金等を取得した場合、5,000万円の特別控除や代替資産の取得による
課税の繰延等といった税の優遇制度が設けられています。
前者の特別控除とは、収用等による資産の譲渡所得の金額(譲渡益)から5,000万円
(譲渡所得の金額は5,000万円に満たないときはその金額)が特別に控除され、課税所得が軽減される、
というものです。
一方、後者の代替資産の取得による課税の繰延とは、収用等によって取得した
補償金等の全部で代替資産を取得したときは譲渡がなかったものとされ、
譲渡所得は課税されません。
また、補償金等の一部で代替資産を取得したときは、代替資産の取得に充てられた補償金等に
対応する部分の譲渡がなかったものとされ、残りの補償金等についてだけ譲渡所得が課税される、
というものです。
なお、収用等により譲渡した資産の取得費のうち、譲渡がなかったものとされる部分に対応する金額は、
代替資産に引継がれます。
◆各種補償金の原則的な取扱い
収用等に際しては、土地等の買い取りの対価としての補償金(対価補償金)のみならず、
これに関連するすべての費用、損失等が補てん・補償されます。
例えば、収益補償金、経費補償金、移転補償金などがその例です。
この場合、これら取得した補償金のすべてが、課税の特例の対象になるか、
というとそうではありません。
特例の対象になるのは、原則、土地等の買い取り部分に対応する対価補償金のみで、
他の補償金は事業所得等の収入金額あるいは一時所得の収入金額となります。
◆例外的な取扱い(補償金の内容を吟味)
しかし、課税実務では、納税者に有利な幾つかの例外的取扱いを認めています。
1)建物等の移転補償金について
移転ではなく、現実に建物等を取壊したときは、移転補償金は対価補償金とする。
2)収益補償金のうち建物の収用等に伴って支払われる営業・家賃減収補償金
この収益補償金は、その建物の対価補償金として取扱われた金額が当該建物の
再取得価額に満たないとき、その満たない金額を、又は不明なとき、
その建物の対価補償金の額に当該建物が木造等である場合は100/65、
その他の構造である場合は100/95を乗じて算出した金額を同建物の対価補償金に振替えることができます。
◆延滞税に関する原則規定
国税通則法の延滞税に関する条文には、
①期限内申告書を提出しながら納付国税をその法定納期限までに完納しないとき
②法定申告期限後に未納税金があるとの修正申告書を提出したとき
などその他の場合に、法定納期限からその国税完納日までの期間に応じ、
その未納の税額に年14.6%の延滞税を課す、と規定されています。
◆二つの延滞税軽減規定
ただし、納期限までの期間又は納期限の翌日から2ヶ月間については、延滞税率を7.3%とする、
との規定があります。
さらに、法定申告期限から1年超後の提出となる修正申告の場合は、その法定申告期限から
1年を経過する日の翌日から当該修正申告書が提出日までの期間を除いたところを延滞税の計算対象期間とする、との規定もあります。
◆こんな事例ではどうなる
申告期限後5年目のところで税務調査があり、増差税額のある修正申告を提出し、
1ヶ月後に納税を済ませたとすると、延滞税の計算対象期間は修正申告書提出までの期間が
1年超なのでその部分は1年に圧縮されます。
修正申告書提出の場合の納期限はその提出日なので、納期限後1ヶ月の増差税額納付は
別途延滞税の計算対象期間となります。
◆どの税率がどの期間に課せられるのか
国税通則法では、法定納期限以後は14.6%、ただし、納期限以後2ヶ月間は7.3%となっているので、
先の例では、延滞税の計算対象期間の最初の2ヶ月と最後の1ヶ月は7.3%で、
残りの10ヶ月は14.6%となるのでしょうか。
そんなふうに読んでしまいそうですが、「納期限までの期間」は7.3%という規定があるので、
本例の場合は全部の期間が7.3%になります。
◆法定納期限と納期限の使い分け
国税通則法や国税徴収法は「法定納期限」について、その各第二条で定義規定を置いているのですが、
「納期限」については特に定義していません。
しかし、両者は異なるものとして使い分けられています。
◆措置法に税率の特例がある
なお、上記の7.3%については租税特別措置法に「公定歩合+4%」(現在は4.3%)とする
特例規定があります。
また、来年からは14.6%部分も含めた大幅な改正が施行されることになっています。
Copyright © 2013 Takada. All Rights Reserved.