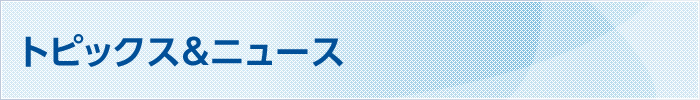
◆税制改正大綱のプラン
税制改正大綱では、国税通則法を改正し、銀行等に対し、マイナンバーによって
検索できる状態で預貯金情報を管理する義務を課す、としていました。
しかし、グリーンカードでの預貯金管理を狙った1980年代での付番はマル優(少額貯蓄非課税制度)口座
重複開設への対策だったものの、現在はマル優預貯金は障害者などに限定適用なので無きに等しく、
むしろ「貯蓄から投資」へと政策が変更し、投資マル優とも言うべきNISA(少額投資非課税制度)を
推進しているので、預貯金への付番の必要性は低下しています。
◆預貯金へのマイナンバー付番はなし
国税通則法のみ、先の税制改正大綱通りの改正案になっていますが、マイナンバー法の改正での
預貯金口座付番のほうは、大義が預貯金保険であり、その緊急的必要性が希薄なため、
強制付番ではなく、任意付番になりました。
預貯金については、口座数の大量性から全てへのマイナンバー付番は無理としても、
新規のものについては義務化するのでは、と推測する向きもありましたが、結果として、平成27年改正では見送られました。
預貯金口座への個人番号の付番を行う場合には、預貯金等へ損益通算範囲拡大の適用条件として
マイナンバー付番口座限定にするものと推測されます。
◆ジュニアNISAには即付番
平成27年度税制改正により、平成28年4月1日から、ジュニアNISAが導入されることになりましたが、
口座重複開設防止の必要性から、マイナンバー付番が義務付けられています。
証券会社等の営業所長に、未成年者口座開設届出書に添付して提出する未成年者非課税適用確認書に
マイナンバー等を記載することになっています。
◆NISAへの付番は遠からず
成人NISAに対するマイナンバー付番については、口座重複開設防止の必要性をマイナンバーで
確保するには既に時機を失しているので、今年は先送りされました。
しかし、法適用上の次の区切りとなる期間開始の平成30年分以後からのマイナンバー付番については、
その効果があるので、義務付けられることになるのではないか、と予想されます。
◆社会保障と税の共通番号開始は16年1月
マイナンバー制度は既に2010年当時の民主党政権時代に税制改正大綱に明記されていました。
自民党政権の13年5月に法案が通り来年開始の予定になっています。
住民票を有する全ての人(日本国民と日本に住所を有する外国人)に対して12ケタの番号を割り当て、
社会保障、税、災害対策の分野で氏名、住所、生年月日、所得、税金、年金等の
複数の行政機関に存在する個人情報を紐付け各機関で情報連携を可能にする、
番号一元管理を目指しています。
◆具体的な使われ方
1.社会保障(年金・労働・医療・福祉) 年金の保険料徴収、資格取得、
確認、給付、雇用保険の資格取得、確認、給付、職安の事務、医療分野の保険料徴収、
給付、福祉分野の給付、生活保護、介護保険、児童手当等
2.税
確定申告書の提出、届出書、納付書への記載、税務署の税務事務、
勤務先での源泉徴収票(従業員、扶養家族)
3.災害対策
被災者台帳作成事務と支援金
◆マイナンバー導入の理由 政府発表
1.所得と行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため不当に負担を免れたり、
給付を不正に受け取る事等は減り、本当に必要な人に支援を回す。
2.国民の行政手続きが簡素化され負担が減る。
行政機関のつながりができるので証明書の交付、確認が簡単になる。
また、自分の個人情報の確認や行政からのお知らせも受け取り易くなる。
3.行政機関側で様々な情報の照合、転記、入力等作業に要する時間が減り、
コスト削減と事務効率が向上する。
◆漠然とした不安
メリットだけでなく懸念材料も認識しておく事は大事でしょう。
・個人情報を集約した情報の外部流出
・個人番号の不正利用、なりすまし等
・一元管理が進むことで人権やプライバシーの面等
国はセキュリティーに関し手立て案を発表していますが、他国でも漏えい、
なりすまし等問題となっているケースもあるようです。
今後利用範囲を民間にまで広げる方向性を示していますので国民にとっての利便性とは
何かを考える必要はあるでしょう。
◆結婚・子育て資金の一括贈与の非課税創設
平成27年4月より「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税」制度がスタートしています。
こちらは「教育資金の一括贈与」の「結婚・子育て」版です。
信託協会によれば平成26年12月現在の教育資金贈与信託の契約数は101,866件、
信託財産設定額合計は6,973億円だそうです。
「高齢者資金を若年世代に移転する」という政策意図に見事にはまったものといえるでしょう。
このような「成功例」もあり、今回の税制改正で「結婚・子育て資金」の非課税制度の創設をみた訳です。
◆「通常額」を「その都度」支出する場合
もともと、扶養義務者から「生活費」又は「教育費」として贈与を受けた場合には、
①金額が通常必要と認められるものであり、
②必要な都度、「生活費」「教育費」に充てられるものについては、贈与税の非課税とされています。
子・孫が父母・祖父母から婚姻後の生活を営むために通常必要とされる家具什器等の
購入資金とするために贈与した場合もこれにあたります。
また、結婚式や披露宴の費用を親などが負担した場合も、式・披露宴の内容や招待客との関係、
地域の慣習の事情に応じて、本来負担すべき者に分担されている場合には、贈与に当たらないこととされています。
◆「一括贈与」のニーズの高まり
ただし、「将来の結婚のために渡しておきたい…」という場合には、
「通常額」を「その都度」という要件にあたらないため、贈与税の課税対象となってしまいます。
このような「一括贈与」を対象として設けられたのが今回の非課税制度です。
20歳以上50歳未満の方が「結婚・子育て資金」に充てるため、
金融機関等との一定の契約に基づき、直系尊属(父母や祖父母)から
①信託受益権を付与された場合、
②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預け入れた場合、又は
③書面による贈与により取得した金銭等により証券会社で有価証券を購入した場合には、
それらの価額のうち1,000万円までの金額については、金融機関等の営業所等を経由して
「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出することにより贈与税が非課税となります。
倒壊の危険性や衛生的な問題がある空き家(特定空き家)に対して、
自治体が解体の行政代執行をできる規定を盛り込んだ「空き家対策措置法」の
全面施行を前に、勧告や代執行の対象になる「特定空き家」の判断基準案を
国土交通省が明らかにしました。
特定空き家への国の取り組み方針を規定した「空家等対策の推進に関する特別特措法」
(空き家対策措置法)の一部が2月26日に施行され、自治体は空き家の所有者を迅速に特定するため、
固定資産税の課税情報を利用できるようになりました。
そして空き家対策措置法は5月26日に全面施行されます。
全面施行後は、自治体が特定空き家の所有者に対して、除却・修繕・立木の伐採といった助言、
指導、勧告、命令ができるようになります。
さらに、改善を促したにもかかわらず放置を続けた場合には行政代執行による
解体も認められます。
解体費用は取り壊し後に改めて所有者に請求することになるそうです。
空き家の所有者は税負担がこれまでの6倍になる可能性も考慮しなければなりません。
地方税法上、家屋が建っている敷地は「住宅用地」として敷地200㎡以下の部分の
課税標準額が更地(固定資産税評価額)に比べて6分の1になる特例があります。
たとえ空き家であってもこの特例は適用されるため、解体費用だけではなく税金面の負担も考えて、
空き家のまま放置している持ち主は多かったのです。
しかし空き家対策措置法では、この税優遇を一定の空き家には適用しないという改正を盛り込みました。
行政の指導や勧告、解体命令の対象になる特定空き家に該当するかどうかの判断基準は、
国土交通省がこのほど公表した資料「『特定空家等に対する措置』に関する適切な実施を図るために
必要な指針(ガイドライン)(案)」で明らかになっています。
これによると、「ネズミやハエ、シロアリの大量発生」「多数の窓ガラスが割れたまま放置」
「外壁が目視でも確認できるほど脱落しそうな状態」などの場合に特定空き家として判断されることになりそうです。
◆ふるさと納税をしている人が増えている
ふるさと納税制度は納税者が、住んでいる場所以外の自治体に寄付し、
寄附金控除として後に税金を軽減する、つまり住んでいる場所の他に納税できるという制度です。
各自治体が「寄附のお礼」として、地元の特産品を提供し、「寄附したお金は税金を払った
扱いになる上、物が貰える」という事で、あまり節税対策等に縁が無かったサラリーマンを中心に、
お得な制度として近年脚光を浴びています。
平成20年に寄附した人(確定申告者ベースで換算)が約3万人だったのに対し、
平成25年に寄附した人は4倍強の約13万人となりました。
寄附の総額を比較してみると、2倍止まりとなっている事から、控除可能額は個人の税額に比例するため、
裾野が広がり、寄附している所得層が拡大しているように感じられます。
◆税制改正でさらに利用増加か
寄附者の増加は、今年の税制改正でさらに勢いがつきそうです。
住民税寄附金税額控除の特例分が、旧来は住民税所得割額の1割が上限でしたが、2割へと引き上げられました。
今まで少額しか控除されなかった方、たとえば年金暮らしのお年寄りの方でも、
控除上限までの寄附をして、お礼の品が貰えるようになりました。
◆自治体も工夫をしている
魅力ある「お礼の品」もさることながら、目的別の寄附を募る自治体も増えています。
美術館の新設や、桜の保護、犬の殺処分をゼロにする、商店街のにぎわいを取り戻す、
ハンドボール中学選手権の存続、難病治療研究等、ふるさと納税の寄附によって、
地元NPO法人や各団体とタッグを組み、魅力ある街づくり、社会的意義の高い寄附を目指しています。
もちろん、地場産業を支えるお礼の品の提供も、立派な地域振興ですが、
自治体が国民に取り組みをアピールするという、総務省が掲げるふるさと納税の意義を鑑みると、
自治体にはクラウドファンディング型の寄附プロジェクトを、もっと考えて、増やして欲しいところです。
Copyright © 2013 Takada. All Rights Reserved.