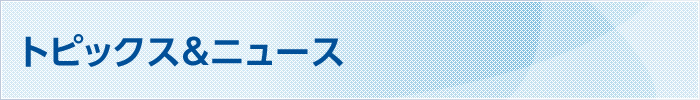
◆雇用保険の加入者となるべきか否か
雇用保険の適用事業所に雇用される労働者のうち、
雇用保険に加入する人(被保険者)と適用除外となる人がいます。
適用となるか否か判断しにくい次のような場合はどうなるでしょうか。
例で見てみましょう。
①法人の代表者・・・個人事業の事業主や法人の代表取締役は被保険者となりません。
②株式会社の取締役や監査役・・・取締役や監査役は委任関係にあるため、
被保険者とはなりません。
但し、取締役であっても会社の部長職や支店長等の従業員としての賃金や
就労実態等から労働者性が強く雇用関係にある人は兼務役員として被保険者になれます。
③事業主と同居の親族・・・事業主の同居の親族は原則として被保険者にはなりません。
但し、事業主の指揮命令下にあり就労実態や賃金が他の労働者と同様で事業主と
利益を共有する地位(取締役等)になければ被保険者となります。
④在宅勤務者…在宅勤務の人は事業所勤務の労働者と同じ就業規則の適用があり
在宅勤務者の業務遂行状況や始業終業等時間管理が明確か等で判断します。
⑤国外勤務者・・・国外での勤務形態が出張による就労者や海外支店への転勤であれば
被保険者となります。
国外出向者も雇用関係が継続していれば被保険者です。
但し、国外での現地採用者は国籍にかかわらず被保険者になりません。
⑥長期の欠勤者・・・労働者が育児休業や介護休業、私傷病で休み、
賃金が出ないときも雇用関係が継続していれば被保険者です。
⑦外国人労働者・・・適用事業所に勤務する外国人労働者は外国公務員や、
外国の失業補償制度の適用者を除き、被保険者となります。
また外国人技能実習生は企業と雇用関係にあるので被保険者となります。
但し、外国人の場合は就労資格による就労可否があります。
⑧2以上の事業場に勤務する人・・・同時に2つ以上の企業に雇用関係がある人は
原則として生計維持に必要な主たる賃金を受けている方で被保険者となります。
平成25年分の所得税等の確定申告から適用される改正がいくつかあります。
新たに適用が始まった復興特別所得税は、基準所得税額
(配当控除分などを元の所得税額から差し引いた後の所得税額)に2.1%の税率を乗じた額が
所得税に上乗せされる税制。
セットで盛り込まれた「復興特別法人税」は平成24年4月から3年間の期間限定でスタートしましたが、
今年3月31日に1年前倒しで廃止される予定です。
一方で復興特別所得税は、平成25年分から49年分まで25年間課税されます。
また、給与等の収入金額が1500万円を超える人の給与所得控除額が245万円の定額に変更されました。
昨年までの確定申告では、収入金額が1千万円超の場合の給与所得控除額は、
収入金額×5%+170万円で算出してきました。
収入金額が1500万円の場合は245万円、3千万円の場合は320万円、
5千万円なら420万円が給与所得から控除できたわけです。
しかし、25年分から245万円が上限になることで、
1500万円超の収入がある人にとっては決して少なくない額の増税となっています。
給与所得者にとって有利になるとされる改正としては、特定支出控除の見直しが挙げられます。
特定支出とは、通勤費用や転居費用、職務に直接必要な研修や資格取得のための費用、
単身赴任時の自宅への旅行費用などのこと。
一定の額を超えた場合、確定申告をすることで、超えた金額を給与所得控除後の金額から
さらに差し引くことができます。
まず、特定支出控除の適用判定の基準が、その年の特定支出の額の合計額が
「給与所得控除額の2分の1(125万円が限度)」を超える場合へと緩和されました。
そして、①税理士、公認会計士、弁護士の資格取得費、②65万円を限度にした一定の図書費用、
スーツなどの制服費用、交際費―などが新たにその範囲になりました。
小規模な同族会社の主宰者と生計を一にする配偶者その他の親族(親族等)が
その同族会社から役員として受ける報酬と個人事業主と生計を一にする親族等が
その事業主から受ける給与の性質は、類似しているようですが、
前者は会社法及び法人税法、後者は所得税法の適用を受け、その効果には差異があります。
但し、役員報酬は「職務執行の対価」として、他方、青色事業専従者給与は
「労務の対価」としてそれぞれ相当であると認められる金額が損金算入、
又は必要経費算入の要件となっています。
◆毎月の支給額に変更があった場合
役員報酬は、定期同額支給といって、一定の場合を除き、
事業年度の中途においてその報酬額を変更すると、
その変更前後の役員報酬の一部が損金算入できません。
なお、一定の場合とは、期首から3月以内の改定や法人の業績が著しく悪化した場合などです。
他方、青色事業専従者給与ですが、個人事業主が青色事業専従者給与として
納税地の所轄税務署長に届けた金額の範囲内であれば、
業績の一時低迷や資金繰りの悪化などにより毎月の給与に変更があったとしても
その支給額については、個人事業主の事業所得、
不動産所得又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されます。
また、年の中途において青色事業専従者給与の支給額を引き上げることも可能です。
この場合の手続きですが、「青色事業専従者給与の変更届出書」を遅滞なく
納税地の所轄税務署に届出ればよいことになっています。
なお、個人事業主が生計を一にする親族等に対して青色事業専従者給与を支給するためには、
その年の3月15日まで(その年の1月16日以後、
新たに事業を開始した場合や新たに青色事業専従者を有することとなった場合には、
その開始した日又は専従者を有することになった日から2月以内)に、
納税地の所轄税務署長に対して「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しなければなりません。
◆未払い計上の可否
法人の役員報酬については未払い経理した報酬についても損金算入が認められますが、
青色事業専従者給与に関しては実際に支給した金額のみが必要経費に算入され、
未払い経理した給与につては必要経費としては認めらません。
◆労働基準監督署が入るとき
昨年の秋にテレビで労働基準監督官が主人公のドラマが放送されていましたが、
労働基準監督署の名前は聞いたことがあっても労働基準監督官が行う事業所調査とは
どのようなものか知っている方は多くはないかもしれません。
労働基準監督署は労災保険と労働基準法(労基法)や労働安全衛生法(安衛法)を
取り扱う部門がありますが、会社が労基法や安衛法を守っているかを調査することがあり、
事業所規模にかかわりなく対象とされます。
◆主な調査の種類は
定期監督で実施される調査ではその年度の方針で調査対象が選ばれます。
この場合は会社が労基署へ必用書類を持って訪問するケースが多いようです。
他には従業員などの申告による調査があります。
従業員や退職者が労基署に申し立て、労基法違反の可能性があれば、
立ち入り調査があったり、呼び出しがあることもあります。
◆労基署調査の流れ
調査は普通書面で通知されてくることが多いので日時、場所、必要書類を確認し、
落ち着いて対応しましょう。
主な指摘事項は次の通りです。
①労働時間や時間外労働時間等の把握はされているか
②時間外労働手当等、割増賃金の支払い
③時間外労働の協定届を提出しているか
④労働条件書面を明示しているか
⑤労働者名簿や賃金台帳の整備
⑥最低賃金は守られているか
⑦従業員10人以上事業所は就業規則を提出しているか
⑧定期健康診断は実施しているか
⑨従業員50人以上事業所は衛生管理者や産業医の選任をして届けているか
⑩管理監督者の時間外労働は適切か
⑪その他、各業種による事項等
以上のような事項をタイムカードや賃金台帳、雇用契約書等を見て、
事業主に確認し、是正事項があれば勧告書や指示書が出されます。
会社は指定された期限までに改善し是正した内容を記して必要書類と報告書を提出します。
すぐには指摘事項の改善が難しくても今後は改善する方向性を示すのがよく、書類を改ざんする等は避けましょう。
◆経営理念は社員に伝わっているか
多くの経営者の方は常にお客様のこと、会社のこと、社員のこと等を考え、
売り上げ拡大、資金繰り、社員のモチベーションアップ等に心をくだいていらっしゃることかと思います。
社員のモチベーションで言えば当然経営者の思いや考えを理解していて欲しいし、
その考えに基づいて働いてほしいところです。
それを「経営理念」に表し、会社の根底となる行動指針を共有している企業もあるでしょう。
では全社員に思いは伝わっていますか?次の問いに答えてみてください。
◆経営理念の浸透度
1、経営理念の明文化
ア、社長はわかっているが明文化してない
イ、明文化している
ウ、明文化し社長の思い考えと合っている
2、経営理念は社内に浸透していますか
ア、一部の社員にしている
イ、全社員に浸透している
ウ、全社員に浸透し、納得もしている
3、経営理念を全社員が実践しているか
ア、理念はあるが実践とまではいかない
イ、一部の社員は実践している
ウ、全社員が実践し、理念が実現している
この質問で3つともウを選択された会社は案外少ないかもしれません。
と言うのは「理念」の意味が分かりにくいこともあるでしょう。
美しい言葉を並べてみてもどれも似たようなありふれたものになりがちです。
それが社員に納得しにくいものになっていたりしています。
◆理念とは根底にある基本的な考え方
経営理念とは言い換えれば会社の存在意義と言えます。
何のために自社はあるのかをわかりやすく表現し、
社会的な意義や人の為になる事等を入れることで社員が理解しやすくなるでしょう。
経営者自らが思いやこだわりを込めた文を作り、
少し時間をおいて練ってから幹部や社員にも意見を訊くのが良いでしょう。
存在意義を明文化することで経営者の大切な思いに共感してくれる社員が残り、
採用でも共感する人が集まりやすくなり、共感できない人は徐々に去っていくかもしれません。
そのような体制が少しずつ進むと組織の活性化が生まれ、
経営者は人使いに悩むことも減ってくるのではないでしょうか。
Copyright © 2013 Takada. All Rights Reserved.