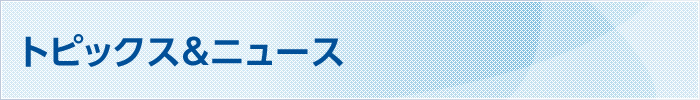
◆税理士のみに「事前通知」が可能に!
平成26年度税制改正において、国税通則法及び税理士法の一部が改正されました。
これによれば、平成23年12月改正(平成24年10月1日から実施)より行われていた
税務調査の『事前通知』(調査を行う旨など法定の11項目を電話(口頭)で通知する制度)について、
税務署が『納税者』と『税理士(税務代理人)』の双方に対して行っていたものを、
今後は納税者の希望により、『税理士』のみの形とすることが選択できるようになったとのことです。
この場合、『新制度』を希望する納税者は、申告書の提出時に添付する新形式の
『税務代理権限証書』の『調査の通知に関する同意』
(調査が行われる場合には、代理人に通知することに同意)欄のチェック欄『□』に
チェックマーク『レ』を入れて頂くことになります(平成26年7月1日以後の提出分より)。
◆一般納税者の気持ちを慮ると…
平成23年改正の税務調査制度の法定化はいろいろと明確になった点
(無予告調査の要件化など)も多かったのですが、この『事前通知』(日程調整の連絡・事前通知項目)が
あまり日常では税務署との接触のない納税者の方にいくと、当初はかなりビックリされておりました。
そのようなこともあって、税理士の側でも、折に触れクライアント様に『税務調査があるときは…』
と周知を行ってきましたが、以前の運用のとおり『税理士のみで構わないのでは…』という意見もかなり出ておりました。
◆H26.3決算でも『前倒し』適用できます!
平成26年4月に国税庁HPには、この『新制度』に関するFAQが早速掲載されております。
これによれば、
①H26.3決算法人がH26.5に提出する申告書にも『事前通知に関する同意』を記載した
税務代理権限証書を添付することが可能なこと、
②これまで提出した申告書について『事前通知に関する同意』をしたいときは、
過年度分について提出する必要はなく、次回の申告の際に、
(新)税務代理権限証書の『過年分に対する税務代理』欄のチェック欄『□』に
チェックマーク『レ』を入れてればよいこと、
③既に提出してしまった相続税申告書に『新制度』を用いたいときは、
『同意』を記載した税務代理権限証書を再提出することなどの取扱いが追加されています。
◆個人株主が破産した場合の自己株式取得
平成26年3月14日付の東京国税局の文書回答事例に面白いものがありました。
平たく言えば『個人株主が破産した場合に、会社がその自社株式を破産財団から
買取った場合には、源泉徴収はしなくても構いませんよね?』という照会です。
この事前照会によると、照会者である会社(当社)の取締役が裁判所から破産手続開始の決定を受けてしまい、
当社の株式がその破産財団に組み込まれてしまったとようです。
当社は非上場であるため、破産財団側としても市場で売却するなどの処分もできず、
当社が時価による自己株式の買取りに応じた―ということでした。
◆通常の非上場の自己株式取得なら源泉徴収
通常、非上場会社が自己株式を取得した場合では、その自己株式の取得により
交付を受ける金銭等の額が当社の資本金等の額(基因となった株式に
対応する部分)を超えるときには、その超える部分が『みなし配当』とされ、
所得税法では配当所得、『みなし配当』以外の部分が株式等に係る譲渡所得となります。
当社の立場から言えば、この『みなし配当』について源泉徴収義務が生じるということになります。
◆強制換価手続きによる非課税規定の射程
所得税法には『資力を喪失して債務を弁済する能力が著しく困難な場合における
強制換価手続きによる資産の譲渡による所得』は非課税とする規定があります。
そこで、照会者は、当社の事案がこれに該当しますよね?と事前照会をした訳です。
一見、この自己株式の取引は、取締役が財産の管理処分権を失ったことにより
株式を組み入れた『破産財団』と『当社』の取引なので、
資力を喪失した取締役(個人)の取引には見えません。
従って、取締役の資力喪失を要件とした非課税の適用は難しいように見えますが、
法律上はこの時点で取締役は財産の管理処分権を喪失していても、
所有権までは喪失していない状態―つまり、取締役個人がまだ取引の当事者という位置付けなのです。
また、この非課税規定の『資産の譲渡による所得』を聞くと、
『譲渡所得』が連想されますが、強制換価による譲渡を原因とする所得を意味するため、
『配当所得』でも非課税であると判断されました。
企業経営では、一般に複数の従業員が、生産・営業・開発など共通の目的・目標を
達成しようとして力を合わせて働かなければならないことが多く、
リーダーシップの巧拙がメンバーの意識・行動を変え、成果を左右することは良く知られています。
◆リーダーシップのあり方
チーム目標を必達するためのリーダーシップのあり方は、
“リーダーの舵取りの下で、メンバーが力を合わせて、自発的に状況判断を行ない、
考え、行動する”方向へ誘導すること、さらに掘り下げれば、
望ましいメンバーの意識。行動を生み出す源泉を確保すること、と言えます。
ある目標に向かってチーム活動が動き出すと、思い通りに、何の障害もなく
進行するなどと言うことは全く考えられず、次々と出てくる障害、問題を解決し続けて行かなければなりません。
それらに対して果敢に対処し続ける力、すなわちチーム力の源泉を、
テーマ・目標設定の段階で確保しておくことがリーダーシップのあり方の基本と言えます。
◆目標必達への源泉を掘り当てる
チームメンバー個々は、専門知識・技術、得意技など異質な人間の集まりです。
そのメンバー個々がテーマ・目標に対して共通の理解と、
どうしても達成したい価値を共有したとき、目標必達への源泉が確保されたと言えます。
このような源泉は、人間の意思。
やる気にあるので、自分達が取りかかろうとする具体的な問題・課題解決テーマについて、
・なぜこの課題解決が必要なのか
・なぜこの目標(達成レベル・時期)が必要なのか
・目標が達成された時の状況(目標が達成されたとき、具体的に何がどのように変化しているのか
・達成プロセスでの自分達個々の役割、協力の仕方
以上のような事柄をチームメンバー全員参加、全員発言で、
突っ込んで話し合うことを通じて、チームメンバーの役割意識、力の合わせ方、
自主的な動き方など、チーム目標必達へのパワーが生まれます。
◆経営者の留意点
経営者は、リーダー達に向かって、チーム力の源泉確保の重要性、スタート段階の話し合いの実践を指導するべきです。
◆次世代育成支援対策の一つ
厚生労働省は育児休業の取得を促すため、雇用保険制度の所得を補う
育児休業給付の拡大を決めました。
今までは原則、子が1歳になるまで給与の50%補償をしていましたが、
平成26年度から育休の当初半年間に限り、3分の2(67%)に引き上げます。
昨年の秋に給付の増額は方針が決まったのですが、次のように発表されています。
◆労働政策審議会報告の概要
「育児休業給付は育児休業を取得しやすくし職業生活を円滑の継続促進するために
雇用保険の失業給付の1つとして設けられている。(中略)
育児休業給付金受給者が増加していることから育児休業の取得促進に
寄与はしていると考えられるが、一方で収入が減るという経済的理由から
育児休業を取得しなかった男女とも一定程度は存在する。
特に男性の育児休業取得率は平成24年度において、
2%弱と伸び悩んでいる状況にあるが男性の育児休業を促進することは
男性のワークライフバランスの実現だけでなく、女性の育児負担を軽減し、
女性が職場で継続して働き就業率向上にも資する。
夫の育児・家事時間が長いほど第2子以降の出生割合が高くなる傾向にあることから
育児休業促進による男性の育児参加の拡大は少子化対策にも資するものになる」
としています。
以上のような背景から今回の給付率の引き上げとなったのです。
◆男女共に育児休業を取得促進できるか
給付率は引き上げられますが、その率は出産手当金の水準を踏まえ
育児休業開始時から6か月間について67%の給付率とすることになっています。
この率は育児休業給付が非課税であること、休業期間中は社会保険料免除措置があり
休業前の税・社会保険料控除後の賃金と比較して実質的な給付はさらに高くなるという計算です。
出産、育児に関する支援措置は労働基準法、育児・介護休業法、雇用保険法、
厚生年金保険法、健康保険法等多岐に絡んでくるので複雑で全体を把握するのは面倒です。
受給率引き上げが必ずしも取得率向上となるかはわかりませんが、
受給者のメリットは増えます。
しかし企業側では取得者が増えると事務面の煩雑や人のやりくりも大変になるという面もあり、
現実的な問題も増えそうです。
消費増税と同時に「すまい給付金」がスタートしました。
すまい給付金申請窓口やすまい給付金事務局で申請受付・審査が始まっています。
住宅ローン利用者の負担軽減制度には住宅ローン減税があります。
この減税制度は4月から拡充され、最大控除額(10年間)が200万円から400万円に、
住民税からの控除上限額が1年あたり9万7500円から13万6500円に増えました。
しかし、住宅ローン減税は納めている所得税から控除する仕組みであるため、
収入が低い人ほど効果が薄くなります。
そこですまい給付金制度は、住宅ローン減税拡充の負担軽減効果を十分に受けられない
収入層が対象とされています。
給付金を受けられるのは、住宅を取得して登記上の持分を保有するとともに
そこに居住する収入が一定以下の人。
住宅ローンを利用せずに即金で住宅を取得した人でも、
50歳以上で収入額の目安が650万円以下の人は対象になります。
給付額は、収入額の目安(都道府県民税の所得割額)で決まる
「給付基礎額」に不動産の「持ち分割合」を乗じて決めます。
具体的には、消費税率8%時は、扶養家族が1人の住宅購入者の場合、
年収425万円以下の人は30万円、425万円超475万円以下は20万円、475万円超510万円以下は10万円。
消費税率が10%に引き上げられたときは、給付対象の上限が775万円以下の人になるとともに、最大給付額が50万円になります。
住宅の要件は、床面積が50㎡以上であること、第三者機関の検査を受けた住宅であることなど。
「新築住宅」と「中古再販住宅」とでは一部要件が異なります。
平成26年4月以降に引き渡される住宅から、29年12月までに引き渡されて入居が完了した住宅までに適用される制度です。
Copyright © 2013 Takada. All Rights Reserved.