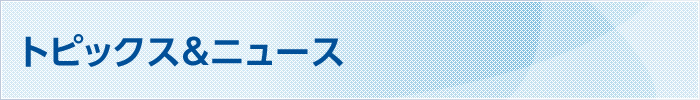
認知症・障害者の方が相続人の場合
◆相続人に認知症や障害者の方がいる場合
遺産分割協議には相続人全員の合意が必要です。
これは相続人の中に認知症の方や障害者の方がいる場合でも同様です。
ただし、その方が意思能力(正しい判断能力)を有していないときは、
遺産分割協議は有効に成立しません。
このような場合、家庭裁判所に「後見開始の審判」の手続きをとり、
成年後見人を選任することとなります。
成年後見人は意思能力を欠いた相続人の代理人となり、分割協議に出席し、
必要な署名等を行うことになります。
(一般に、後見人は、その相続人の不利益にならないように、法定相続分程度の遺産を取得できるよう協議を進めるようです)
◆所得税・相続税の障害者控除の適用
成年後見制度における成年被後見人(家庭裁判所において「精神上の障害により
事理を弁識する能力を欠く常況にある者」として後見開始の審判を受けた者)については、
H24.8の名古屋国税局文書照会で所得税法上、障害者控除の適用となる「特別障害者」に
該当することとされています。
また、相続税法上の障害者控除の適用となる「特別障害者」については、
所得税法上の障害者控除の対象となる「特別障害者」に該当する者と規定しているため、
介護認定が低く、障害者手帳の交付を受けていない方でも、「特別障害者」として所得税・相続税の障害者控除の
適用を受けることができます(H26.3東京国税局、文書回答事例)。
◆「納税管理人の届出」を後見人宛てに
成年後見制度は「自己の財産の管理・処分」を「することができない(後見相当)」
「常に援助が必要である(保佐相当)」「援助が必要である(補助相当)」という判断能力の程度により
3種類に分かれています。
財産管理委任契約(見守り契約)を締結する場合には、「納税管理人の届出書」を
納税地(本人)の所轄税務署に提出し、申告書等の送付先・連絡先を成年後見人宛にすることで、
税金関係も後見人に対応してもらうことができます。
また、成年被後見人・被保佐人は会社法により取締役になることができません。
取締役の方に成年後見人が付いた場合には、直ちに役員変更を行わなければなりません。
◆税制調査会で検討される
安倍内閣は新しい成長戦略の中で子育ての負担を軽くしたり、
企業に登用を促したりする女性の社会進出の後押しを進めようとしています。
専業主婦等に有利な社会保障制度の見直しの検討を始めました。
人口減と高齢化が進む中、労働力確保と質の向上が持続できる社会にするため、
女性の労働力率を上げてゆくという観点から長く議論されてきました。
配偶者控除の扱いはこれからどのように変わろうとしているのか見てみたいと思います。
◆配偶者控除の境界103万円の壁
しばしば出てくる「103万円の壁」とは配偶者(妻)の収入が年103万円以下の世帯で
夫の所得税の負担を軽くする仕組みです。
妻の年収が103万円以下なら夫の年収から配偶者控除として一律38万円を控除します。
妻の年収が103万円超から141万円未満の間であれば配偶者特別控除があり、
38万円から3万円の範囲で行われます。
また、多くの企業では夫が配偶者控除を受けられる妻がいる場合に
家族手当を支給するところが多いのも現状です。
さらに妻の年収が130万以上になると健康保険の被扶養者と国民年金の3号被保険者からも外れ、
妻自身の社会保険料がかかるようになります。
就業調整は103万円、130万円の時に行われることが多いといえるのかもしれません。
このような制度であると労働時間を抑える就業調整する人が多いといわれています。
◆見直しが与える影響
配偶者控除に代わるものとして議論されているのが家族控除です。
妻の年収にかかわらず、夫婦で76万円を世帯の控除額とする案です。
これは今まで配偶者控除を受けていた世帯では負担増になりそうです。
制度変更で可処分所得が減れば収入を増やそうともっと働こうとするかもしれません。
パートよりフルタイムへ、より高い賃金へと移動するかもしれません。
ただし実際は長時間働きたい人ばかりではないでしょう。
現在国民年金の3号被保険者は保険料がかかりませんが
2016年10月からは従業員501人以上の企業で、週20時間以上勤務、年収106万円以上の場合は
社会保険に加入することになっています。
税制と併せて社会保険の動きも見ていく必要があります。
◆トライアル雇用とは?
職業経験の不足等から就職が困難な求職者をハローワークから雇い入れ、
3カ月間の試行雇用する事でその適性や能力を見極めてから常用雇用へ移行することを目的とした助成金です。
今まで紹介元はハローワークが紹介した人が雇われた場合が支給対象者でしたが
2014年3月からは一定の要件を備えた職業紹介事業者や大学の紹介による場合も
支給対象者とされることになりました。
民間職業紹介事業者は「雇用関係給付金の取り扱いに係る同意書」を主たる事務所(本店等)の
所在地を管轄する労働局に提出しておくと、その取り扱いを行うことができます。
◆支給対象者の拡大
以前の支給対象者は主にニート・フリーターや母子家庭の母等でしたが、
それ以外に学卒で未就職者や育児等で離職後キャリアブランクのある人も対象とされました。
次のいずれかの要件を満たしたうえで、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。
①紹介日時点で就業経験が無く職業に就くことを希望する者。
②紹介日時点に学校卒業3年以内で卒業後安定した職業に就いていない。
③紹介日前2年以内に2回以上就職や離職を繰り返している。
④紹介日前において離職期間が1年を超えている。
⑤妊娠・出産・育児を理由に離職し、紹介日前の時点で安定した職業に就いていない期間が1年を超えている。
⑥就職支援をするのに特別な配慮が必要な一定の該当者。
◆支給額と手続き
原則3ヶ月のトライアル雇用を行い、支給額は1人につき月4万円。
最長3カ月で12万円支給されます。トライアル雇用の選考中の人数は求人数の5倍までで、
それを超えた人数は対象になりません。
受給手続きは求人の際、トライアル雇用を受け入れる旨を申し出ておき、
雇い入れから2週間以内に実施計画書を提出します。
トライアルが終了した時は終了した日の翌日から起算して結果報告書兼支給申請書を提出します。
試行後常用雇用にならなかった時でも申請はできます。
欧州連合(EU)の欧州委員会は米アップル・米スターバックス・伊フィアット子会社の3社に対して
正式に税務調査を開始したと発表しました。
3社は、グループ会社を置いたアイルランドなどでEU法の規定以上の過剰な税制優遇措置を受け、
公正な競争を阻害した疑いがあるそうです。
アップルやグーグルなどの多国籍企業に対しては、米議会が租税回避行為の
可能性を指摘するなど批判が強まっていて、EUもその流れに沿って国際的な租税逃れの
追及に乗り出した形です。
欧州委によると、3社はそれぞれ、アップルはアイルランド、スターバックスはオランダ、
フィアット子会社はルクセンブルクで、各国の政府から不当な税制優遇を受けて
納税額を抑えた懸念があるとしています。
たとえばアップルがアイルランドに納めている法人税の実効税率は約2%となっていて、
欧州委はこうした税率の低さが、アップルとアイルランド政府の間での
「特別な税制優遇の合意」による疑いがあるとして、今後調査を進めていく予定です。
アップル社は欧州委の発表に対して「特例的な優遇措置をアイルランドの政府から受けたことはない」と発表。
アイルランド政府も「ルールに抵触していない」とコメントしています。
多国籍企業の多くは、グループ企業内でモノやサービスを取り引きして税率が低い国に
利益を移転する手法を取っており、税収を取りはぐれた各国の税務当局は
そうした企業の姿勢を「租税逃れ」として追及を強める構えを見せています。
◆長期存続の要因とこれから大事にしたい事
少し前の調査ではありますが、帝国データバンクの長寿企業調査で、
創業100年以上の企業に対し、「長期に存続してきた要因と今後重視したい事」のアンケートによると
要因の1位は「本業を中心とした経営と品質の保持」でありました。
2位以下は「堅実な経営」「資金の安定調達・運用」「顧客ニーズに沿う」「リーダーシップの貫徹」と続き、
6位には従業員の育成が入っています。
従業員の育成は今後重視したい事の1位であり、以下、「販路拡大」「コスト削減」「後継者の育成」
「顧客ニーズへの取り組み」等が続きます。
◆調査結果を見て今後大事な事
アンケート結果を見て企業が存続して行くのに大事な事は次の3つになるでしょう。
ア、経営革新に取り組む
イ、社員を大事にする経営
ウ、継続後継者の育成
各々を検討してみますと、
アの経営革新については事業戦略と言う面と経営システムの革新と言う面があります。
社内システムでは仕事のやり方を変えるには直接影響を受ける社員への説明も必要になるでしょう。
イの社員を大切にする経営では育成が今後取り組みたい事の1位ではありました。
OJTやOFF-JTのどちらの研修も大事です。
しかしむしろやる気を高めるという点で「衛生要因」となる会社方針、職場環境、給与、対人関係等があり、
これが不十分であれば不満足と感じます。
もうひとつの「動機付け要因」では仕事内容、責任、目標達成、承認、昇進、成長などの
可能性を見出すことで満足が高まると言われています。
働きやすい職場環境と部下の成長につながる仕事を与え、
責任を持たせ評価処遇につなげる事で社員との信頼関係を築く事が大事です。
ウの継続後継者の育成は最も重要でしょう。
経営革新も社員を大事にする経営も取り組みの先頭に立つのが経営者です。
経営者がこれらの重要性を認識しなければ何も進みません。
会社の存続、社員の力の結集、市場環境の変化を読み取り経営革新を行う、業績を上げるだけでなく
企業倫理も意識する時代です。
実務能力と人的能力があり信頼される人柄が求められているでしょう。
Copyright © 2013 Takada. All Rights Reserved.